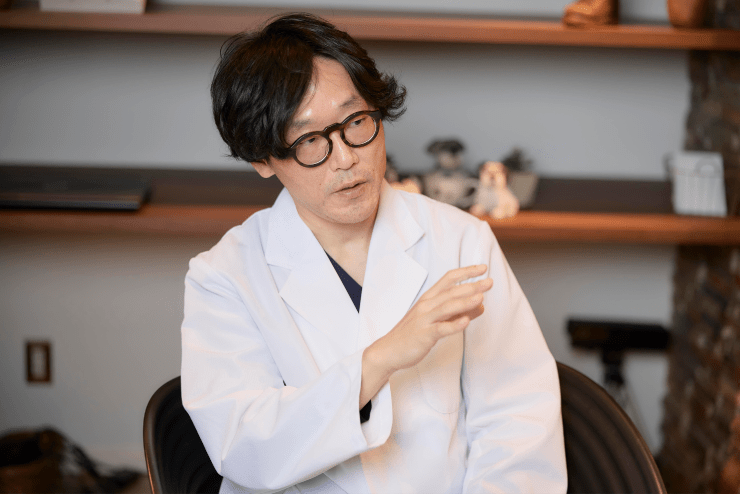
第三回
時代にあったトップ
〜ボスからリーダーへ〜
若手獣医師が長く勤務してくれない……。病院スタッフが院長に求めるものは、時代の変化とともに変わりつつあります。特に二次診療では、技術継承や人材育成は大きな課題です。これまでさまざまな病院で人材育成をご経験されてきた澤木和貴先生に、これからの時代、どのように若手の先生を育てていったらよいか、どのような仕組みが求められるか、お話を伺いました。
澤木 和貴
(さわき かずたか)
神経疾患の画像診断と内科症例をメインに担当するほか、外科手術にも対応。MRIによる診断が必要となる事が多い神経疾患において、一次診療院の先生方と連携し、動物ならびにご家族のQOL向上に貢献している。特に画像診断が好き。
二次診療こそチーム医療を

人材育成や技術継承は、二次診療であればこそ重要な課題であり、人材の離職は病院として大きな財産の喪失になります。では、若手の先生の働きやすさや人材育成の方法とは何か。それは時代の変化とともに変わりつつあると思います。
以前は、院長のカリスマ性や求心力で病院を引っ張っていく時代だったと思います。しかし、専科の細分化が進んでいる中で、これからはより深い領域でアップデートが求められます。また、DX化の波は獣医療業界にも達しており、病院経営にも多様な要素が加わり、アナログな一個人のスキルだけでは、それらすべてをカバーしきれなくなっています。自分の手が届かない分野を補ってくれるような人材を集めて協力体制を築くことが、これからの時代には求められていると思います。そのためには、従来のトップダウン式の組織ではなく、互いをリスペクトし、支え合うことができる関係性が理想です。というのも、院長がもつスキルや知識量が、常に唯一の最適解であるとは限りません。自分が知らないことや足りないことを若い世代に任せることも、院長、ひいては病院全体として大事なことだと思います。
「客観性のある評価制度」の作り方
評価制度は働きやすさにつながるので、当グループでは強く意識しているポイントです。院長の主観に依存するのではなく、客観的にスタッフを評価する仕組みや制度が大切だと考えています。
まず、各スタッフが自己評価シートを作成します。その評価を基に、管理職クラスの獣医師たちがディスカッションを行い、最終的な評価が決まります。人間同士ですから相性はありますが、特定の個人との相性が悪いからといって低評価にされてしまうのは、評価される側としては納得できない部分があります。当グループでは複数名が評価に関わることで客観性を担保し、被評価者自身が納得して次への糧に変えられるようにしています。
技術的なキャリアアップに関しても、一定の条件を満たさないと手術ができないというクリアな制度があるので、明確な目標に変えられます。
せっかく当グループを選んでくれたのであれば、極力、長く一緒に働きたいと思っています。もちろん、病院のスタイルや仲間の雰囲気に対して、全員が100%適応できるとは限りません。ですが、ただ「上司と合わないから辞める」「いつまでも手術できないから辞める」といったことにならないように、複眼的に評価できるよう徹底されています。
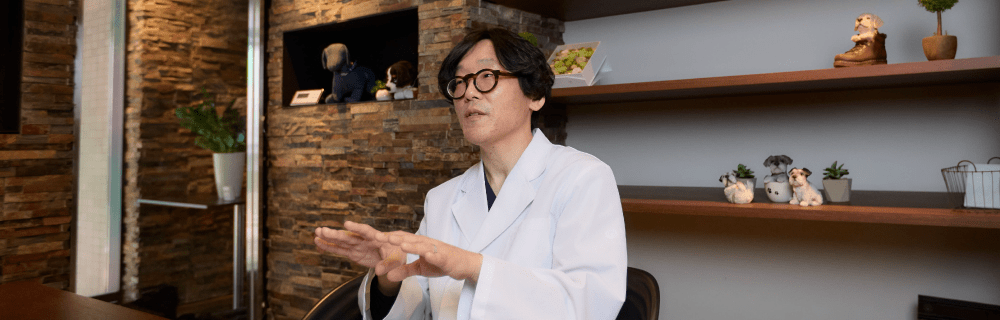
上司と合わない=おしまい じゃない !
当グループでは、経営陣は経営陣、フロントはフロントというように、組織と役割が分担されており、常にフラットな目線で対応できる体制になっています。例えば、獣医師である我々にも経営陣との定期的な面談の機会があります。フロントだけでは解決が難しかったり、直接相手には伝えづらいようなことも、相談しやすい環境となっています。組織が独立して存在しているため、そこから情報が漏れることもなく、一人で思い詰めずに済みます。
症例は1人ではなく皆で診る
わからなければ相談できる体制があるというのは、過度なプレッシャーによるストレスを排除することにつながります。自慢のようになってしまい恐縮ですが、当グループの強みとして、カルテや症例データを共有している点が挙げられます。そうすることで、困った症例があってもすぐに同様のケースを検索できます。また、症例に関していつでも相談ができるように、グループ内、病院ごと、個人間のチャットツールがあります。「わからない症例があります」と投稿すると、皆で解決のための議論が開催されます。「症例は皆で診る」という土台があるので、一人で抱え込むことなく「わからない」と隠さず報告できるのです。
この風通しのよさは、当グループの大きな特長だと感じています。私が若い頃は、日々の業務量ゆえに満足な回答が得られないようなこともありましたが、今は違います。特に、若い先生はわからないことがあるのは当然です。だからこそ、それを素直に打ち明けることができる環境は、若手の成長に必要不可欠です。
とはいえ、何事も手取り足取り教えるわけではありません。極力自分で考えて動く。その上で、詰まったところを一緒に考えるようにしています。可能な限り自分で判断する習慣を大切にしつつ、寄り添いフォローアップする体制も整っています。
こういった方針にしているのは、もう1つ理由があります。それは、モチベーションの問題です。常にやることを管理され、自由のない働き方を強要されると、「やらされている感」をもってしまうようになります。そういった環境では息苦しさを与えてしまい、若い先生は合理的な傾向があるので、成長できる環境を求めて病院を見限ってしまう可能性もあります。そのようなことを防ぐためにも、不安を抱え込む必要がなく、その上で、自分でやるべきことを判断し、行動できる環境を提供することを大切にしています。

皆がより幸せになれる未来のために

動物病院を健全に存続させ、医療品質を持続的に発展させていくためには、相応の収益が必要です。多くの動物を救い、対価を得て、従業員に還元し、さらなる発展の源泉を確保する。私は、獣医師の役割はそのサイクルの中心として駆動することだと考えており、常に意識するようにしています。また、正当な対価を得ることは、自身の腕を磨くモチベーションにも繋がります。
若い先生に対しては、まず前提として、自分がされて嫌だった経験をさせないことを徹底しています。私が若い頃は今ほど教育環境が整っていなかったため、修行期間が長く、遠回りしました。もちろんすべてが無駄だったわけではなく、積み上げた当時があったから今があることは間違いありません。
ですが、効率的な教育をすれば、私が5年かけて学んでいたことを1年で習得し,成長曲線を伸ばすこともできます。それによって、残りの4年でさらに多くのことを学び、私の臨床5年目とは比べものにならないほどの人材になれる可能性があるわけです。そして優れた獣医師が増えるほど、それだけ多くの患者さんやご家族が幸せになれます。
私自身、トップに立つのは自分である必要はないと考えています。若い先生は、どんどん知識と技術を吸収し、できるだけ早く私を追い抜いてほしいと願っています。最初からできる人はいないので、興味があり悩んでいるであれば、まずは前に進んでやってみることがよいと思いますし、当グループはその体制が整っています。
CLINIC NOTE 2025年6月号より転載
